オークションやネットショップで購入した陶磁器が正しい物なのか知りたい。
自宅に昔からある陶磁器の正体が何か知りたい。
でも、鑑定士に頼むのは怖いし、せっかくだからまずは自分で調べてみたいと考えている方もいると思います。
このページでは自分で行うセルフ鑑定の方法を教えます。
そもそも鑑定とは類推
古陶磁の鑑定は基本的には類推=類似するものと比較し推定する行為です。
特に古ければ古いものほどこの類推することが多く、その比較対象をどれだけ見てきたか、どれくらい理解しているかが鑑定の精度に関わってきます。
逆に言えばこの100年程度に作られたものでない限り、100%決定づけることはできないのが鑑定とも言えます。
どうやって類推をおこなうか
では類推はどのように行なっていくのがいいのでしょうか。
ご自身で鑑定をする際にまず参考になるのは
「美術館や研究機関の古陶磁と比較する」ことです。
美術館や研究機関の古陶磁と比較するための方法は大きく2つございます。
簡単に沢山の情報を得れる書籍を見る、質感などの比較のために美術館で実物を見る。
まずはこれらのことから比較してみてください。
骨董屋にも古陶磁は多くございますが、自身の鑑定のためだけに骨董屋に見にいくのは失礼でし難しいと思います。
また、骨董屋自体の真贋も合っているとは言い難いのでおすすめいたしません。
セルフ鑑定におすすめの本や書籍

実は古陶磁の鑑定の仕方そのものを専門とする書籍はほとんどございません。
90年代には多少なりありましたが、その難しさや秘匿性から今ではほとんど存在していません。
※一応、一部の窯に限定したものは存在はいたします。(備前焼など)
そのため、陶磁器の写真集や目録、研究書籍を自分なりに落とし込んで鑑定に照らし合わせていく必要があります。
陶磁器に関する本は大きく分けて幾つかございます。
・写真が多い陶磁器をまとめた書籍
・文章も多い研究書籍
・美術館の出している図録
それぞれ違いとどのように使うべきをご紹介します。
写真が多い陶磁器をまとめた書籍

この書籍は一般的な出版社から発行され、一つのジャンルに絞ったものが多いです。
例えば天目茶碗を集めたもの、高麗茶碗を集めたもの、仁清の品を集めたものといった具合です。
この手の本は美術館や個人の収蔵品の写真が掲載さており、写真での比較がしやすいものとなります。
おおよそ30~50点程度の写真を見ることができます。
また、比較的金額も安く、流通量も多いため入手しやすく初心者におすすめです。
文章も多い研究書籍

こちらは一般的な出版社からも専門的な出版社からも発行され、一つの窯についてより詳しく解説している書籍です。
写真は載っておりますが前述の書籍に比べて小さく少ない印象です。
文章での情報が主となっており、窯の成り立ち、場所、土について、作り方、釉薬などの情報をより知ることができます。
コツが必要ではありますが、書籍の写真や美術館の美術品と照らし合わせ、より鑑定を確かなものにできます。
こだわって集めている窯があるのようであれば、専門の書籍を一冊持っておくのはおすすめです。
美術館の出している図録

美術館が所蔵されているコレクションや季節ごとの展示の際に発行する図録です。
一つのテーマに絞って発行され、一般的な書籍よりも更に写真が多く、更に大きく綺麗に掲載されています。
100~300程度の写真を一つのテーマで見ることとができるので、一番おすすめです。
また、図録のほとんどには個々の陶磁器の解説がついているので陶磁器を比較する上で見るポイントになります。
ただ、書籍と違い発行部数が少なく、期間限定の発行のため、入手ができないものも多くございます。
美術館で実物を見る

陶磁器の情報を見るために美術館や博物館に足を運ぶのも大切です。
写真や文章ではわかりづらい、釉調や土の厚み、質感、大きさなどを見ることは重要です。
あと、少しオカルトチックに聞こえるかもしれませんが、その陶磁器の持つ雰囲気を見ることが大事です。
特に中国の場合、その陶磁器自体が宮廷や儀式に使われていたこともあり、その場にそぐわない風貌であるかどうかは大切なのです。
陶磁器を見るのにおすすめの美術館や博物館は下の記事にまとめておりますので、併せてご覧ください。
類推をするために見る陶磁器のポイント
では、自分で鑑定(類推)するために陶磁器のどこを見比べるのがいいでしょうか。
これを知っておくと自分で鑑定をする際に何を見るべきかわかります。
土

例)16世紀頃の古唐津の土
土の運搬が難しい時代の古陶磁はその窯の近隣で採れる土を使います。
長く続いている窯だと時代ごとに使う土が変わることもございます。
その時代、その地域に合った土かを見ることは真贋の基本と言っても過言ではありません。
例えば、釉調と形が合っていても土が合っていない場合には時代違いや贋作を疑うべきです。
※ただ、この150年くらいの現代物はインフラの進歩により土は運べてあまり参考になりません。
土は高台など露胎している箇所から見ることができます。
高台の作り

例)12世紀頃・南宋官窯の高台
高台の作り方は窯や作家により特徴が多く現れます。
畳付けの幅はどうか、高台内の削り込み、大きさ、支持具や石目跡の有無、ろくろ目などを美術品と照らしあわせます。
ただ美術館では接地しているため高台はまず見れまぜん。
高台の多く載っている書籍を探す必要がございます。
全体の器形

例)12世紀頃の龍泉窯の鳳凰耳瓶
実は陶磁器の形は窯、時代、そして作家によりある程度決まっております。
特に時代による流行のようなものがあり、窯が違っても似たような形のものが作られることもございます。
また中国や朝鮮は宮廷や儀式での使用も多く、それに沿った形なのかも重要です。
一見同じように見えても比率が全然違ったりするので、形については見る目を養う必要がございます。
釉薬・釉調・顔料

例)14世紀頃の龍泉窯の釉薬
釉薬も同様にその窯、そしてその窯の時代ごとの変化と合っているかを見る必要がございます。
ただ、土や形と違い、古い時代の釉薬は成分が現代ほど厳密にできず、攪拌ムラなどもあり同じ時代でも結構色が違います。
必要な鉱物の入手量なども影響するため、写真だけでなく歴史的背景などの知識も覚える必要はございます。
綺麗だから本物、汚いから偽物というものでもなく、需要なのは他の要素との組み合わせです。
焼き方、焼成温度

例)朝鮮半島の高麗青磁特有の石高台
古陶磁はその時代、地域、規模によって窯の仕組みが変わります。
また、窯によって焼成時に高台に支持具をつける、珪石をつける、匣鉢に入れるなどの焼き方の技法が違います。
そういった仕組みを高台や土の焼き具合、釉調の変化から読み取り比較いたします。
時代経過の具合

例)16世紀頃・黄瀬戸のカセ
古いものなので時代が経過をするとともに変化や劣化をしていき、貫入やカセなどが起こります。
その時代経過がちゃんと起きているかは鑑定のポイントとなります。
しかし、悪意を持って贋作を作るために古く見せる方法もあるので、古そうに見える=古いものではないということに注意が必要です。
絵付けや装飾のモチーフ

11世紀頃・鈞窯の龍耳
絵付けや装飾などに使われる模様やモチーフは国や窯、時代、作家などによって違いがあります。
特に古い品のモチーフには吉祥の意味が込められているものがあり、その意味も含めて適した使われ方がしている必要があります。
例えば中国では龍は皇帝の模様となりますが、それが庶民の使うものに使われているのは違和感があります。
また、模様のモチーフが合っていても描かれ方や形が合っているかも見なければいけません。
落款や窯印

例)12世紀頃・南宋官窯修内司の落款
窯や作者の証となる落款やサインの有無、そしてその書体や模様が合っているかは鑑定における一つの要素となります。
しかし、この落款は正直にいうと簡単に真似ができてしまいます。
模倣品を作る上で一番騙されやすいものであり、同じ落款があるから本物であるという考えに陥らないことが大切です。
特に江戸時代の野々村仁清や尾形乾山といった作家は落款を押しただけの偽物が出回っています。
ただ、現代作家において作者が不明なものものを特定するのにはとても役に立つ情報です。
鑑定で参考にできない箱や箱書き
鑑定の際に箱や箱書きはもちろん鑑定の要素とはなりますが、最新の鑑定技法においては重要視されません。
というのも箱書きは後からでも書けてしまうこと、また箱と中身を入れ替えられていることがあるためです。
そのため、箱や箱書きは鵜呑みをしすぎると鑑定のドツボにハマってしまいます。
由緒ある伝世をしているもの以外は参考にしすぎないほうがいいでしょう。
ただ、大正時代後期から昭和以降の作家物は作家数が多いため、特定するのに箱は参考となります。
セルフ鑑定は経験とセンス
セルフ鑑定はもちろん簡単なものでなく、多くの陶磁器と見比べて調べて、比較や類推により答えを導き出します。
難しい話をすると、美術品と見比べて似ていると感じるかは人により感覚が違い、正直経験だけでなく、そのものを読み解くセンスが必要です。
その工程はとても大変ですが、ぜひ楽しんで骨董の世界によりハマってほしいと思っています。
答え合わせにぜひオンライン鑑定を
当オンライン美術館では写真によるオンライン鑑定を行なっております。
金額は2000円からと低価格で行えますので、セルフ鑑定に行き詰まった際や答え合わせに是非ご利用ください。
名称・国・時代・窯(地域)・真贋・釉薬・解説・参考美術品の鑑定が可能となっています。
写真と寸法を送るだけで家にいながらできるので割れ物を運ぶ不安もございません。


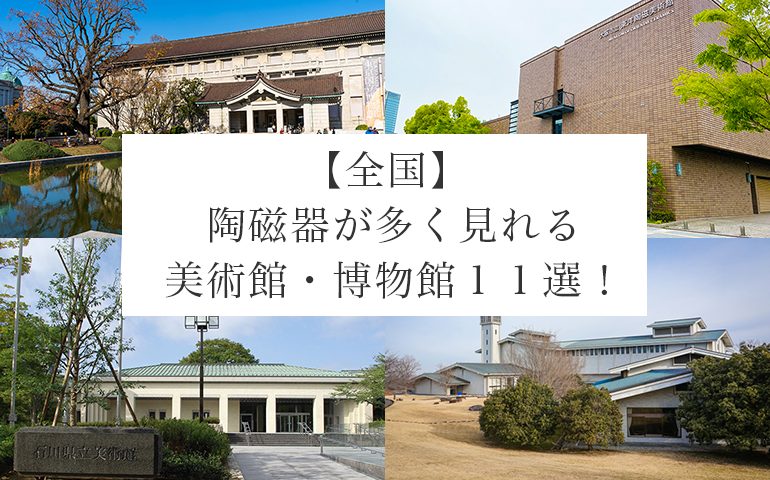




コメント